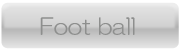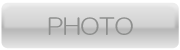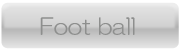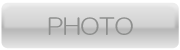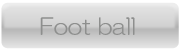 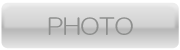 
 1988 to 2004 五つ星のディスク達 1988 to 2004 五つ星のディスク達 |
| その2へ |
1988年
The Stone Roses
The Stone Roses
|
私的採点:★★★★★
何事にも「始まり」というものがある。
いうなれば、このアルバムがオレの音楽の始まりだった。
当時の日本の音楽シーンは当然ながらインターネットの恩恵など無く
世界のムーブメントから2〜3年は遅れていた。
このアルバムと出会ったのも、実際には1991年あたりだったと思う。
ちょっとした偶然をキッカケに、姉の持っていたCDから、買ったばかりのウォークマンに
押し込まれたこのアルバムは、これまで聞いていたどの音楽とも違う音色を奏でていた。
それでも中学に入るか入らないかの小僧に、ロックの真髄など分かるはずも無く
このアルバムの真の価値が見出せるまでに5年を要することとなる。
1996年。日本ではVロック全盛。
高校生といえば、ヒットチャートを作っている世代と言ってもいい。
ご他聞にもれず、ヒットチャートの音楽を聴き漁る中で、このアルバムだけは特別だった。
唯一といってもいいほど、永遠に輝き続けるアルバム。
そして、UKロックからその全てが明らかになった時、このアルバムは絶対の存在となる。
極東に住む、予備知識ゼロの少年を虜にしたそのバンドは、すでにこの世には存在しなかった。
何度聞いても、その度に違う表情を見せるアルバム。
一回聞いて、ピンと来て使い捨てられるような音楽ではない。
何度も、何度も聞いて、気づくと離れられなくなっている。
ロックで、ファンクで、グルービーで…
ヘビーでソフトで…
「ロックンロールの魔法」
初めて、その魅力に取り込まれてしまった 始まりの一枚 である。
|
1995年
OASIS
Morning Glory?
|
私的採点:★★★★★
再生された回数で言えば、他の追随を全く許さない。ダントツの一位だろう。
これほどまでに愛したアルバムは無い。
ローゼズが始まりの一枚だとすれば、これはそこからを決定付ける一枚。
それまでローゼズ一枚だったUKアルバムが何百枚とCDラックを埋め尽くすことになったのは
全て、この一枚のせいである。
そして、日本のヒットチャートを気にしなくなったのも、このアルバムのせいだと思う。
世界では、こんな音楽が鳴らされている。
直球なのに、目が離せない。
圧倒的。
まさに、世界の中心で彼らは歌っている。
オレ達が、現代のビートルズ。ローリングストーンズ。
どこを切っても紛れも無くベストソング。そして究極のバランス。
我々の世代で最も愛されているアルバムであるような気がする。
|
1991年
NIRVANA
Never mind
|
私的採点:★★★★★
オレの部屋には一枚だけアーティストのポスターが張ってある。
それは、ただこちらをじっと見つめている。
決して死など感じさせない力強い眼差し。
しかし、同時に全てを見透かすような眼差し。
90年代の前半は、世界がグランジ一色だった。
中学生だったオレはグランジなど意識せずに、グランジファッションをしていた気もする。
服屋に行けば、そんなファッションが大半だったからだ。
実際にこの作品をちゃんと聞いたのは、すでにカート・コバーンが頭を打ち抜いた後だった。
アルバムジャケットから、その音楽性、歌詞、全てが世界に衝撃を与えた。
世界は、このアルバムを表現できる言葉を持たず、グランジという称号を作り出した。
後に、グランジと呼ばれる全てのものは、グランジではない。
唯一、ニルヴァーナだけがグランジなのだ、とオレは思う。
この作品を聞くときに、絶対やってはいけないのが
精神的に参っているときに聞いてしまうこと。
全てに対して虚構になってしまうか、
内から沸き起こる衝動を抑えきれなくなるか。
感受性が強ければ、アチラ側に持っていかれてしまうかもしれない。
人の精神を根底から叩きのめす作品である。
|
1994年
Green Day
Dookie |
私的採点:★★★★★
ロックキッズの尊敬を一手に引き受けた作品。
青春と表現するのに最も適したアルバムだろう。
誰が、いつ、どこで聞いてもハマってしまうようなキャッチーな魅力。
疾走感と爽快感。
とにかく流行った。
邦楽しか聴かないような人間でも、このアルバムは聴くだろう。
同時に、日本のバンドが次々にこの作品にインスパイアされ、多くのフォロワーを生み出した。
MTVではマイケルジャクソンを抜いて、最も人気のあるPVとなった。
少年の頃に持っている、今にも弾けそうな何かを
完璧に表現したアルバム。
何年たっても、この作品を聴けば、青春のあの頃に戻れるタイムマシン。
|
1994年
OASIS
Definitely Maybe |
私的採点:★★★★★
オアシスのデビューアルバムは、ビートルズへの敬意に溢れながら
それを、リバプールではなく
マンチェスターという自分達のバックグラウンドで消化した作品。
それが、オアシスという新しいスタンダードとなり
世界の中で、英国を代表する音楽性を生み出した。
アルバムの構成力で言えば、歴史的名盤の次作を上回る。
あるべきポジションにあるべき楽曲が存在し、
聞くもの全てを強引に納得させる。
夜明けの雨の中で
魂の深淵まで滲み通るような雨の中で
痛みを感じながら、永遠にいき続ける。
このアルバムで行き場を探していた嗜好性が
ガッチリと固まったように思う。
モーニング・グローリーと共に、
オアシスの中では絶対に外せないアルバムであり
神の生み出した作品と言ってもいいだろう。
|
1996年
Radiohead
the Bends |
私的採点:★★★★★
デビュー作で見せていた抒情的な楽曲は
このザ・ベンズで、よりスケールを拡大させ
radioheadが本当の才能を秘めた恐るべき存在であると
世に知らしめた。
いまや「ロックの古典」とも言われるほど
必ず聴いておくべき一枚に指定される。
ベンズを買った時には
すでにOKコンピューターがリリースされた後だったので
ベンズの位置づけは確立されていた。
それは紛れもなく”現代オルタナティブの頂点”という称号である。
ただし、ある意味でギターロックの限界を示してしまった
作品であるかもしれない。
19の時に、このアルバムを死ぬほど聞いた。
もちろん大学の4年間は、
あらゆるアルバムを死ぬほど聞いているんだけど
ザ・ベンズはその中でも突出した存在。
今でも、秋の良く晴れた日には
このアルバムを聴いていた頃を思い出す。
|
1997年
Radiohead
OK Computer
|
私的採点:★★★★★
しんしんと降る雪の中で
ザ・ベンズを聞き込んだ後に満を持して購入した
OKコンピューター。
前作でギターロックを極めてしまった彼らが次に向かう方向は
決して同じ一本道ではなかったことが伺える。
爽快感よりも、むしろ胸につまるようなモヤモヤしたものを、
決して吹き飛ばすことなく、ムリヤリ消化させようとする。
陰鬱な闇の時には、さらに深く、深く。
この世に救いなんて無いかもしれないと、歌う事で
それすらも気づかない連中に比べれば、
いくらかマシだという事を気づかせてくれる。
Radioheadのアルバムを聞くならば、
リリース順に聞くことを強くお勧めしたい。
それは、この作品のみらず、以降の作品にも言えることで
Radioheadが音楽シーンを変えるほどの絶大な影響力を示すと
言われるゆえんを体感できるからである。
20世紀最高の一枚といわれるこのアルバムは
その名に恥じることなく素晴らしい出来栄えである。
ただし、それは誰にでもすんなりと受け入れられるような
明快さを併せ持ったものではなく、
むしろ混沌を混沌のまま示した作品である為
聞き手に、反芻作業を要求する内容であると言わざるを得ない。
それが行われて、初めて”次のカタチ”を見せてくれるアルバムだった。
|
2000年
Radiohead
KID A |
私的採点:★★★★★
2000年10月
世紀末に、突如として放り込まれた
ロック史上最高の問題作。
これをロックという定義においてよいのかすら
疑問に思えるほどの作品は
当初、OKコンピューターを聞き込んだ同志が
発売されたばかりのKID Aを聞いて、何人も頭を抱え込んだ。
音楽誌に踊る「絶賛」と「酷評」の二分論。
恥ずかしながら、20歳のコゾーは試聴機の前で立ち尽くし
購入する予定だったこのアルバムを棚に戻し、
グリーンデイの新譜だけを買って帰った。
そして半年後。
新世紀に前触れもなく産み落とされた双子のアルバム
「Amnesiac」を聞いたことで、事態は劇的に変化を遂げる。
AmnesiacはKID Aの翻訳本である。
個人的にはそう思う。少なくとも、自分にはKID Aと立ち向かう時に
このアルバムが必要だった。
聞き直したKID Aは、それまで生きてきた中で
最も衝撃的な勢いで脳内を駆け巡った。
「ロックの神様が降りてきた」とはこういうことだろう。
それまで、何度聞いても理解できなかった無機質な音の塊が
まるで、だまし絵を解いた時の様に受け入れられた。
それはまた、何度聞いても違う表情で迎え入れてくれた。
さらに半年後、ゼンハイザーのHD580で聞いた時には、
もう、このアルバムが絶対に手放せなくなっていた。
無人島で一枚だけ持っていくのであれば、ローゼズやオアシスをさし置いて
このアルバム以外にはありえないだろう。
飽きることのない作品。
何の怖れもなく、これまでのradiohead像を叩き壊し
新時代の幕開けを告げた究極のアルバム。
この作品に出会えた事を感謝したいと思わせる一枚である。
|
1998年
The Verve
URBAN HYMNS
|
私的採点:★★★★★
OASISと並ぶマンチェスター臭漂うUKサウンド。
つくづくストーンローゼズの影響を感じさせる、個人的な選定基準。
陰鬱なUKの曇り空を連想させながら
どこまでも広がるスケール感。
「アンセム」と呼ぶに相応しいビタースウィートシンフォニー。
これほど壮大で鮮やかな幕開けにも関わらず、幸福感は感じない。
喜びはあるのに、楽しさはない。
この不思議な感覚は、先の見えない道を進むため
前に進むしかないという決意の表れ。
未来は誰も、何の保証をすることもできない。
不幸もあるし、幸福もある。
それでも時は流れるし、一日は必ず朝から始まる。
|
1997年
Blur
Blur |
私的採点:★★★★★
ブラ―とは、最初の出会いで
間違ってこのアルバムから入ってしまった為に
以前のアルバムを聞くたびに違和感を覚えてしまう。
大してインターネットの普及していない時代に
オアシスのライバルであるという僅かな情報だけで手に入れた
バンドの名を冠したアルバムは
このバンドの最高傑作であると思う。
パークライフというブラ―の真の代名詞的なブリットポップを経ずに
このアルバムに辿りついてしまったことで、
良くも悪くも、この作品の全てを肯定的な目線で受け入れることができた。
一言で言ってしまえば、喪失感と倦怠感。
村上春樹的な雰囲気の漂うアルバムだが、そこにキザな表現などは一切なく
むしろ打ちのめされた傷を隠そうともしない、裸のブラ―がそこにあった。
ゴリラズのデーモンの原点は、ここにあるような気がする。
恐らく、これまでブラ―を敬遠していた男性たちからも
多くの共感を得るきっかけになってあろう。
ただし、以前のブラ―を愛する、愛しすぎた人々にとっては
ブリットポップからの脱却は裏切りに等しい行為だったはず。
その辺の間違った解釈をせずに済むということでは、
知識不足というのはマイナス面だけではないということである。
|
1998年
OFFSPRING
AMERICANA
|
私的採点:★★★★★
ハードコア全盛。
その中でもオフスプは、頭一つ抜け出た存在。
スピード感、爽快感、アクの強さ、全てが絶妙のバランスで成り立ち
アメリカーナという名作が生まれた。
メロディラインもさることながら
力強さとテクニックという土台がしっかりしているからこそ
キッズだけでなく、あらゆる層の年代から支持を受けることができたと言えよう。
そのするとキャッチーな展開から、
一度聞いただけで耳に残る作品に思われがちだが
何度も聞くことで意外な実験性も垣間見ることができる。
ただし、オフスプのLIVEになってしまえば話は別。
とにかく煽りまくって、ボルテージ全開で望むべし。
|
1994年
Weezer
Weezer |
私的採点:★★★★★
アメリカの泣きのロック。
今でこそ「草食系」や「メガネ男子」などのジャンルが確立されているが
マッチョな時代のアメリカにそんなものは存在しなかった。
さらに言えば、そんなセンスの良い楽曲などではなく
ただひたすらに、己をさらけ出すだけの無防備な音。
アメリカの非モテ集団のバイブルとなっただけでなく
潜在的に国民レベルで同様の意識を備えた日本に歓迎された。
ちょっと女々しすぎる音楽なのに、芯が強いおかげで
全く嫌な感じがしない。
あんまりねじれた音楽ばかりを求めなかった、10代の時に聞けたので
抵抗なくハマることができた。
どこまでも純粋な一枚。
|
1997年
FOO FIGHTERS
THE COLOUR AND
THE SHARP
|
私的採点:★★★★★
ニルヴァーナの幻影。
それを振り払うためのバンドだと、デイヴ自身も疑わなかっただろう。
それが、このアルバムで吹き飛んでしまった。
色々な思いを込めて聞いた全ての人間をぶっ飛ばした
モンキーレンチ。
ニルヴァーナの終わりじゃない。フーファイターズが始まった。
デイヴ・グロールの才能が弾けまくった瞬間である。
ハードなのにラフさよりも、統一感が溢れている。
そして、どこまでも続く爽快感。
いつ聞いても、清々しい気分にさせてくれる。
このアルバムをカートが聞いたら
「デイヴ。お前はオレと違って才能に溢れているよ」
そう言うような気がしてならない。
頭の中をカラッポにすることができる
清涼剤として、文句なしの作品。
|
1999年
FOO FIGHTERS
THERE IS
NOTHING TO LOSE |
私的採点:★★★★★
待ちに待ったフーファイの新作だった。
このアルバムを手にとって震えがきた。
当時は知識量の少なさを補う為、
国内版を優先的に買っていたので、帯がついていたわけで。
「失うものなどなにもない」
本当に失うものが無かったのがネヴァーマインド。
失うものが大きすぎたその後のニルヴァーナ。
失うものすら失くしたフ−ファイの始まり。
新しく積み上げた THE COLOUR AND THE SHARP。
その後に出したアルバムに書かれていたこの一文。
このタイミングで失うものがないと言い切るセンス。
帯を書いた人、ありがとう。
貧乏学生だった時期に2500円出して買うアルバムは結構な出費だったが
これは、当時ですらその10倍の価値があると信じて疑わなかった。
完成度、というレベルでは圧倒的である。
誰が聞いても満点をつけられる。
これだけアグレッシブな作品にも関わらず、聞き手を選ばない柔軟さ。
どんな人にも、自信を持っておススメできるアルバムである。
|
1998年
MANSUN
SIX |
私的採点:★★★★★
隠れた名作。というのだろうか。
インターネットがこれだけ普及した現在では、そんな「発見」の喜びは少ない。
このアルバムも、もはや圧倒的な認知度を有している。
しかし、当時はこのアルバムは
「知る人ぞ知る名盤」だったのである。
特に、本国UKで叩かれながら、いち早く日本のセールスが好調だったことから
日本人の耳が確かだったことが伺える、感慨深い作品。
ゆったりと始まり、まるで夢の中のようなサイケな世界。
ビートルズのサージェントペッパー〜に似た感覚だ。
あまりにも独特のメロディ。美しく、クセになる甘美な感覚。
こういったアルバムを意図して「実験的」に試みるアーティストは多い。
狙った通りのリアクションを得られるかどうかは紙一重である。
しかし、このアルバムの凄いところは『狙った感』が全くないことである。
通学中に聞いていると、現実感が無くなって
危ない感じになってしまうことがよくあった。
|
1991年
MY BLOODY
VALENTINE
LOVELESS |
私的採点:★★★★★
マイブラは後追いである。
というか、並みの音楽の聞きこみ方ではこれは理解できない。
20歳になってようやく、足を踏み入れることを許された。
何故、1991年にこのアルバムができたのか。
悲しいかな、日本人では絶対に到達し得なかった世界である。
11歳でこれを聞いていたら、俺の人生は間違いなく狂っていただろう。
再生ボタンを押した瞬間から流れ込む轟音。
ハードロックやヘビーメタルなどとは全く違う、ただ・・・轟音。
轟音のモヤに一筋の光。
よく寝る前に爆音で聞いていた。
どうやったら、こんなノイズの海で眠りの世界に入れるのか
自分でも不思議でしょうがないが、何故かものすごく落ち着く。
20年経った今でも、マイブラの音楽は誰にも真似ができない。
古いとか、新しいとかの概念に囚われない、別次元の音。
この世界観に、死ぬまで好きになれない人もいるかも知れない。
でも、その前日にでも好きになれたら、幸せに死ねるだろう
|
1991年
PRIMAL SCREAM
SCREAMADELICA |
私的採点:★★★★★
これも19歳くらいで購入したアルバム。
いわゆるバリバリのUKロックの王道だと思い込んでいたので
少し肩透かしを食らったのを覚えている。
そんなわけで、購入後しばらくは棚の中に眠っていたわけだが
ひとしきりロックを聞きまくった1年後くらいに改めて聞いて
ぶっ飛んだわけで。
楽曲的に難解なわけではなかったので
段階を踏まないと理解できないアルバムだとは思っていなかった。
しかし、久々に出会ったこのアルバムの、何とも新鮮な感覚。
まるでロックの応用編のテキストである。
初心者お断りだが、基本を押さえた人間にはこれほどツボな音はない。
|
1996年
BECK
ODELAY |
私的採点:★★★★★
ジャンル不明。
今となっては珍しい話でもないが、
当時はBECKをカテゴライズすることは不可能であり、
かつ新ジャンルの登場というわけでもなく、
とにかく取り扱いに困るほどのスケールの存在であったのは間違いない。
ビジュアル先行の雰囲気も相まって異常な人気を博していたので、
あまり良いイメージを持っていなかったが
一聴してコイツはやはり天才である。そう表現するしかない出来栄えだった。
単純にセンスが良いとかそういう次元の音ではない。
ただ、このアルバムに関しては難しいことは考えずに
とにかく、だら〜っと聞いていれば、それだけで心地よくなれる。
|
1997年
Fountains of wayne
UTOPIA PARKWAY
|
私的採点:★★★★★
純粋な良盤を聞きたければ、このアルバムは最高の一枚である。
基本がしっかりしているので
捻り具合も抜群に安定している。
直球勝負でこれだけの音楽を鳴らしながら
なおかつアルバムとしても成立させることの難しさ。
まさしく名盤といっていいだろう。
曲ごとのメリハリの聞かせ方があり、
まるで映画を見ているような気分にさせてくれる。
そんなに知名度の高いバンドだと思っていなかったので
知る人ぞ知る名盤だと思っていたのに、
名盤特集で意外なほど、隅の方に毎回載っているメジャー盤である。
|
1999年
Stereophonics
performance and
cocktails |
私的採点:★★★★★
最初にイギリスのバンドだと聞いていなければ
間違いなくアメリカのバンドだと思ってしまう。
ザラザラとしたボーカルに伸びやかなメロディ。
UKで言うところの、いわゆる「労働者階級」(ブルーカラー)の音楽。
それでいて、どことなく上品さを残したセカンドアルバム。
これ以降はどんどんUS寄りにいってしまうので、
USとUKの中間に位置した、時期的にも貴重な作品である。
ステフォの知名度は本国に比べると、日本では圧倒的に低い。
カイザーチーフスやレイザーライトのように、独特の感じがするわけでもなく
むしろ、日本ウケするメロディセンスのバンドなのに。
どことなくクセのある中でも、爽快感の溢れる楽曲が並び
絶妙のバランスで成り立った名盤。
|
1999年
TRAVIS
THE MAN WHO |
私的採点:★★★★★
誰もがデビューアルバムと思ったトラヴィスの2ndアルバム。
これによって国民的、世界的なバンドになった出世盤。
冬の曇り空というジャケットがピッタリなメロウで儚げな作品。
異例のロングヒットを続け、彼らのキャリアの分岐点ともなった。
このアルバムを機に、パンキッシュな部分は鳴りを潜め、
ある意味、一度バンド自体が解体されたかのような作品を作り続ける。
そういった意味ではアンダーワールドに近いのかもしれない。
作品全体の統一テーマとしてあるのが
「ソングアルバム」
トレンドに左右されることのない、永遠のメロディーだろう。
力みのない、情景を感じさせる必聴の一枚。
|
1997年
U2
POP |
私的採点:★★★★★
U2といえば、現在のロックシーンで
最も巨大な発言力を持つバンドではないだろうか。
1億7千万枚のアルバムセールスと22のグラミー賞。
そのキャリアは疑いの余地がない。
エモーショナルで壮大なメロディーを引っさげ
アイルランド特有の陰鬱さと透明感を残しつつ、受け入れやすい音楽を表現する。
そんな中、90年代より突如エレクトロ路線を歩みだす。
しかも、それはどことなくキナ臭く、安っぽさを表面に出し、
世界は欺瞞とフェイクに満ちているかのような表現であった。
そしてこのPOPを最後に、U2は原点回帰に立ち戻り、
往年のファンを狂喜させた。
そういった意味では、カメレオンのように色を変えた
ミラーボールのようなアルバムは、世間的な評価は低い。
しかし700万枚を売りながら、キャリアの中で、谷間に位置されるバンドなど
U2ぐらいのものだろう。
実際に、このアルバムを聞いてみると、U2の本質からは少し違う場所にある。
しかし、あまりにもでかいU2という色眼鏡を取って聞いてみれば
信じられないほどの完成度と遊び心、そして感動に満ちている。
|
1997年
IAN BROWN
UNFINISHED
MONKEY BUSINESS |
私的採点:★★★★★
伝説のバンド、ストーンローゼズが解散し、
不安と期待の渦巻く中、リリースされたアルバム。
ローゼズは、ジョンスクワイアの天才的なメロディーセンスを
レニとマニの絶大な安定感を持った演奏力で昇華し、
そこに危うさと、不安定さを兼ね備えた愛すべきイアンのボーカルが
一つになって、完成される奇跡の音楽。
その再現は、どうあがいても出来るわけはなく、
問題は、不安定なイアンだけのボーカルが、成立できるのかという
1点に尽きるのみであった。
しかし、それはこの作品で良い意味で裏切られる。
もちろんLIVEではなく、収録の音源のため、ボーカルは安定しているのだが
ローゼズの後半で見せた、イアンのマリミュージックに寄せたセンス。
USに比べ、大いに遅れをとっていたブラックミュージックの雰囲気を
マリという独特の文化から、微妙に取り入れ、唯一無二の音楽性を確立した。
それがイアンのボーカルにがっつりとハマり、
名盤と呼ぶに相応しい作品となった。
|
1992年
MANIC STREET
PREACHERS
GENERATION
TERRORISTS |
私的採点:★★★★★
攻撃的でありながら、美しいメロディライン。
いまは亡き(正確には原因不明の失踪のまま死亡と認定)リッチーのセンスが光る
デビュー&解散(予定だった)アルバム。
実際には、今でも現役の国民的なバンドとして
長期にわたるキャリアを築くことになっている。
リッチーが失踪してからは、壮大なスケールを武器に
ヒットを飛ばしているが、このデビュー盤は、もっと敵意に満ちた
ヒリヒリするような作品だった。
しかし、ハイライトはやはり後のヒットにも繋がる壮大さを隠し持った
モーターサイクル〜であることは否めない。
それでも、やはりアルバム全体の魅力は、誕生と同時の死という危険さが
はらんでいたことに他ならない。
|
1998年
MARILYN MANSON
mechanical animals |
私的採点:★★★★★
このアルバムを語る上で、コロンバインの銃乱射事件は
切っても切り離せない。
それは、ロックが「暴力の元凶」と弾圧された典型的な事件である。
犯人の少年が聞いていたこの神をも恐れぬ破壊的なメタルラウドネスは
あのマトリックスでも使用されたスピード感の塊である。
マリマンが暴力を引き起こすという強引な解釈は
犯人の少年がハマっていたボウリングというスポーツが持つ
暴力性を立証するのと同じレベルの話だと某映画監督は語っている。
あくまでも音楽のみで語るとするならば、
これだけラウドでありながらキャッチーさを残し、なおかつメロディアスな
楽曲を兼ね備えたこのアルバムは、掛け値なしに名盤ということである。
|
|
その2へ |
|
|