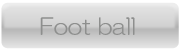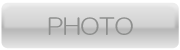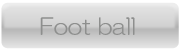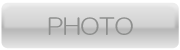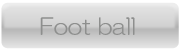 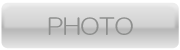 
 1988 to 2004 五つ星のディスク達 1988 to 2004 五つ星のディスク達 |
| その1へ |
1991年
Red Hot Chili Peppers
BLOOD SUGAR SEX
MAJIK
|
私的採点:★★★★★
前ギタリストのヒレルがオーバードーズで死に、
その悲しみを乗り越えるように加入したジョンのギターは
アンソニー、フリー、チャドの才能と相まって想像を絶する作品を生み出した。
ストリートのヒーローの殻を突き破り、
世界的なバンドの仲間入りを果たした名盤。
白人でありながら、黒人の持つファンクさを併せ持つ
まさにアメリカの中のアメリカバンド。
力強いLIVEパフォーマンスは評判を呼び
最強バンドの称号を手に入れた。
これまでの音楽シーンに風穴を開け、日本に「ミクスチャー」という
独特のジャンルを形成させるに至った革命的なアルバム。
|
1999年
Red Hot Chili Peppers
CALIFORNICATION
|
私的採点:★★★★★
このアルバムが持つ意味はとてつもなく大きい。
ボロボロの状態で敗北を認め、それでもバンドとして歩み直すことができた。
自分達のルーツを見つめなおし、あるがままに音を奏でる。
ジョンフルシアンテが復帰した、レッチリのアルバム。
これを復活作と呼ぶのは、少々気が引ける。
何故なら、これは歩みを進める作品ではなく、ただ自分達を見つめるだけの作品。
負け犬であると歌うだけの作品。
表面的なマッチョさを売りにしてきた最強バンドは
決して強くなどはなく、見せかけだけの敗者でしかなかった。
自分達が何者であるかを知り、心の強さを手に入れたことで
レッチリは最強のバンドとなることができた。
そんな、ウソ偽りのない「真の強さ」に呼応した世界中の人間が
このアルバムを世紀の名盤だと認めるにいたっただけの話である。
ファンクさとパンキッシュだけでなくメロウな中にまで魂を込めた
楽曲たちは、4人にしか起こせないケミストリーを生み
結果的に爆発的なセールスを、ロングスパンで遂げることとなった。
|
2002年
Red Hot Chili Peppers
By the Way
|
私的採点:★★★★★
カルフォルニケイションの、意外ともいえるほどのセールスを受け
世界中が注目していたレッチリの次の一手は
気負うでもなく、実に自然に現れた。
これこそが本当の復活と言っていいだろう。
敗北を歌ったカルフォルニケイションから、歩みを始めたバイザウェイ。
ジョンのギターは冴え渡り、手探りだったパフォーマンスは
成熟の時を迎えた。
ブラッドシュガーの絶頂期を知るものは、
あれ以上のパフォーマンスが見られるとは思っていなかっただろうし、
ジョン脱退時の危機を知るものは、バンドが生き返るとは思っていなかった。
そして、絶望と歓喜の入り混じるカリフォルニケイションを経て
この名盤が生み出された。
名作を1枚出せば、スペシャルなアーティストだが、
2枚連続で出せば、それは歴史に残る偉業である。
そして、間隔を開けて、尚その偉業を達成するのならば
それは奇跡に等しいとさえ思うのだ。
|
2000年
THE STROKES
is this it |
私的採点:★★★★★
2000年。
世紀の終わりと始まりの年。
そんな年に、相応しすぎる、一枚のアルバムである。
新しい何かを求めていた人々は、このシーンに風穴を開ける音楽を待っていた。
明らかに、次の時代を作り出すバンド。
スピーカーから流れる、古臭いはずのガレージロックは、
回顧主義的な雰囲気を一切見せずに、全く新しい感覚で鳴り響いた。
この一枚から、多くのガレージに傾倒したバンド達が
シーンにムーブメントを巻き起こすことになるのだが、
どれだけ上手くやろうとも、やはりこの作品ほどの衝撃は現れない。
ストロークスというアメリカの新人バンドが
ピストルズやニルヴァーナの時のような破壊力を
これほどの軽快なメロディのみで見せつけたのである。
時代を象徴する定番の一枚。
|
2000年
EMINEM
The Marshall Mathers |
私的採点:★★★★★
世にあるロックが多様化し、その価値を見誤り始めた世紀末において
マーシャル・ブルース・マザーズ3世=M・M 通称エミネムがもたらした功績は非常に大きい。
ラッパーというポジションでありながら
明らかにロックというジャンルに鉛の弾をぶち込んだアルバム。
一歩間違えれば、ただの低俗な悪口や自慰的な吹聴にしかならない歌詞が
日本人ですら心地よく感じる、素晴らしくメロディアスな芸術的リリックによって
黒人の黒人による黒人の為の音楽で、白人が成功した稀有な例となった。
実際のLIVEでは、アドリブのスラングで韻が繰り出されるので
ネイティブでないとスピードについていけない感がある。
また、バックグラウンドの理解力を必要とされ、黒人社会や白人社会のあり方
アメリカの差別社会や労働状況、家庭環境に世界情勢まで絡んできたりする。
この辺りを日本のファンがどこまで理解できるかは分からないが
パブリックな毒舌キャラクターというスタンスで、
分かりやすくそれらを世に知らしめている点には頭が下がる。
本来、ロックやパンクが担っていたはずの役割をエミネムが代弁しているという
その意義においても非常に重要な作品である。
|
2001年
Muse
ORIGIN OF SYMMETRY |
私的採点:★★★★★
2001年時点でMUSEというバンドはLIVEパフォーマンスの上手い
「そこそこのバンド」という位置づけだった。
LIVEによってそれらが昇華されていって
2010年には、世界中のフェスでトリを努められる存在となった。
そんなMUSEの2枚目には、Plug in babyというキラーチューンが存在する。
しかし、このアルバムの真意は全体を通じて、ソリッドで大仰なMUSE像を示したことにある。
作品ごとに作風を意図的に変えるアーティストが多い中、むしろ自分達の作風を貫くことで
シーン自体にMUSEを確立させてしまったバンド。
非常に聞きやすいキャッチーな作風の中に
飽きの来ない複雑かつ壮大な味付けがなされている。
さすがに20代後半で、このアルバムに出会ってしまっていたら
やや辟易してしまったかも知れないが、若かりし時期に聞き込むことが出来た為に
共に過ごすことができた名盤。
|
2001年
Sugar Ray
Sugar Ray
|
私的採点:★★★★★
ある晴れた夏の夜明け。
ガラガラの西湘バイパス。
当時のことを思い出すと、少し悲しい思い出だったなあと、
あれから10年経っても切なくなる。
超個人的な思い入れが入り混じる作品だけど
流れるようなメロディと、見事なまでの夏のイメージ。
直接的な表現がないにも関わらず、情景が伺える秀作である。
日本での評価は、爽快なサーフバンドという感覚であり
実際に、それ以上でも以下でもないのだが
アメリカではそういったニーズ自体が必要であり、扱いは小さくない。
ある意味で、最も青春を感じさせる作品である。
|
2000年
JJ72
JJ72 |
私的採点:★★★★★
美しすぎるハイトーンボイスに透明感のあるメロディ。
一聴して漂うヨーロピアンな雰囲気。
どことなくキーンのデビューアルバムと重なる部分があるが
彼らより一足早く登場し、そして消えてしまったバンド。
思えば、このデビュー版の雰囲気からして
息の長い活動の予感はできなかったが、
その儚さゆえに。より美しく感じたのかもしれない。
成長してしまうと失われてしまうだろう一瞬の輝き。
絶妙なバランスで成り立っていた一枚。
|
2001年
NEW ORDER
GET READY
|
私的採点:★★★★★
ジョイ・ディビジョンにおいてイアン・カーティスを失った
ニューオーダーと呼ばれるバンドは、確執を抱えていた。
このアルバムがリリースされるまでに費やした期間は8年。
リアルタイムでのニューオーダーなど全く思い入れのない世代に
本当のマッドチェスターを教えてくれた衝撃の一枚。
ストーンローゼズ、オアシス、プライマルスクリームの原点がそこにあり、
現在進行形のグルーヴィーなロックがかき鳴らされていた。
爽快感は全く感じないのに心地よいダンサンブルな音。
調子外れな部分があるのに、ツボにハマってしまう音。
アルバムを通してまさしく衝撃の連続だった。
中毒性があるくせに、即効性は無く、ジワジワと蝕まれていく感じ。
誰もがハマるかどうかは分からない。
人によってはヘタをすれば不快感を感じるかもしれない。
そこには、バーニーとフッキー、スティーブンモリスのプロ意識の塊・・・
悪い言い方をすれば、険悪な関係性が上手くケミストリーを起こしているのか。
彼ら以上に気難しかったという、亡きイアンカーティスのいた
ジョイ・ディヴィジョンが存在していたら、と連想させてしまう
理路整然とした狂気の作品。
|
2001年
Ash
FREE ALL ANGELS |
私的採点:★★★★★
イアンブラウンのヘタウマとはちょっと違うのだが
決して上手いとは思えないVoにも関わらず、聞き入ってしまう
不思議な魅力。
10代で彗星のように現れ、栄光と挫折をあっという間に味わった
Ashの会心の復活作となった。
デビューの時よりもみずみずしく、輝きを放った作風のアルバムであり
グランツーリスモ2の楽曲にも採用されていた為、ゲーム中も含め
恐ろしいほど繰り返し聞くことになったアルバムでもある。
デビューアルバムの荒削りな部分が補正されているこのアルバムは、
3rdアルバムというより新生デビューアルバムといった風合いである。
演奏力が格段に向上したことで表現がより具体性を帯びて豊かに感じられる。
若々しいけど子供っぽさは無い。
素晴らしいアルバムだと思う。
|
2002年
THE MUSIC
THE MUSIC
|
私的採点:★★★★★
世紀末において一度、解体されてしまったロックは
行き場を見失ったかの如く、多様なシーンの影響を受けて
ある意味で混乱をしていたように思う。
そんな中で、おとずれたUKの子供達の革命。
特に、日本で圧倒的な指示をもって受け入れられた作品だ。
恐らく、その要因の一つとして、歌詞自体に深く固執することなく
音楽と、パッションによって表現されたアルバムだったということが考えられる。
同年の赤坂ブリッツでの鮮烈なLIVEは10年近く経った今でも
忘れがたい貴重な経験だ。
あの時の自分の全てがあそこにあった気がする。
個人的にも凄く思い入れのあるバンドだし
日本人であれば誰もが受け入れられる作品だと思う。
同時に、今ではちょっと繰り返すことが出来ない時期を悲しく感じてしまう。
|
2002年
The LIBERTINES
up the bracket |
私的採点:★★★★★
世界的な重要度と衝撃では、MUSICを上回るリバティーンズのデビュー作。
スミスやピストルズ。クラッシュなんかと比較されるほどのアルバムである。
いつの時代も変化することの無い若者の鬱憤を表現ている。
その時々で必要とされる役割を担ってくれた存在だ。
ストロークスの切り開いた道を、リバティーンズという色でロンドン風に染め直した。
いかにも英国らしい皮肉に満ちた音楽は、退廃的であり
予想に違わず、自滅してしまうのだが
こと、作品においてはとてもクリエイティブで、実はスキがない。
今、聞いてもロンドンの風景が色あせずに浮かんでくる。
時代のトレンドを思いっ切り取り入れているにも関わらず
全く古臭さを感じない不思議なアルバムである。
|
2002年
MANDO DIAO
bring em in
|
私的採点:★★★★★
ビッグインジャパン。
本国スウェーデンと日本では圧倒的な人気で受け入れられたアルバム。
スェーデンという国籍が災いしているのか?
UKでの評判がいまいちというのが不思議である。
その風貌からしてビートルズを意識したモッズスタイルで
楽曲は、へヴィパンクモッズという印象だ。
流れるような展開でノリの良い楽曲が、やや単調ではあるが
ムード歌謡の雰囲気をもったバラードなどもあり
LIVEは非常に盛り上がった。
アルバム全体でのバラエティ性や、シーンに与えた影響などを考えると
確かに革新的ではなかったかも知れないが
消費されるだけの音楽という見方をするには、あまりにも惜しい秀作である。
|
2002年
COLDPLAY
A RUSH OF BLOOD
TO THE HEAD |
私的採点:★★★★★
デビューアルバムが激賞されながら
やや物足りなかったコールドプレイの飛躍の一枚。
一発屋ではないことを証明したばかりか
疑わしい評価をしていたメディアを屈服させた。
作品全体のクオリティが非常に高い上に、バランスが取れており
クールな旋律がアルバムを支配している。
それは、後にシングルカットやCMに使用される曲の多さからも伺える。
この作品が評価される所以は、キャッチーすぎず、難解すぎず
それでいて、時折ハッとさせるほどの印象を残すこと。
繰り返し聞き込んでも、決して嫌味にならず
まるで風景の一部のように受け入れられる名盤。
この作品を皮切りに、コールドプレイは後のスターダムに
登りつめていくことになる。
|
2004年
John Frusciante
Shadows Collide
With People |
私的採点:★★★★★
全体で一曲であると思う。
名盤は、多分に漏れず、そう言われるのだが、
通常は曲ごとに切っても素晴らしさが損なわれることは多くない。
この作品は、残念ながら単発で聞いてしまうと、その魅力が半分以下にまで
落ち込んでしまう、やや特殊な作品である。
永遠に晴れることのなさそうな情景を描いたアルバムジャケットは、
まさにジョンの性質を現している。
レッチリとして歌うにはあまりにもジョンフルシアンテ色が強すぎたのだろう。
バイザウェイを脱色したかのような、原色のままのジョンの音だ。
ソロとして、痛々しいほどのありのままの自分を出しているがゆえに
充実している時期にありながら、幸福に満ちた感じはない。
魂を削りながら、音を紡ぎ、歌っている。
このまま歌い続ければ、いずれ燃え尽きてなくなってしまうのではないか。
そんなアーティストとしての叫びを感じることが出来るアルバムである。
|
2004年
THE VINES
WINNING DAYS |
私的採点:★★★★★
オーストラリアのバンドでありながら、
オージーにありがちなノリと勢いを重視したバンドなどではなく
むしろUKよりのメロディと内向したヘヴィネスをはらんだヴァインズ。
デビューアルバムにあったメロディンセンスはそのままにも関わらず
やや、メロウに偏ったが為に、一部のメディアからは「後退した」という評価を受けた。
しかし、特筆すべきは、そのメロウな楽曲であり、
アルバムタイトルでもあるウィニングデイズこそが
このアルバムを名盤たらしめている象徴であると感じている。
情緒不安定なクレイグの精神状態が生み出すメロウな曲は
どこか自嘲気味でもあり、思わず抱きしめたくなる。
|
2004年
GREEN DAY
american idiot |
私的採点:★★★★★
9.11から世界のロックは一変した。
あらゆるアーティストが反戦をテーマにした作品をリリースする中、
被害者の立場であるアメリカ人でありながら、その後のアメリカの対応に対して
痛烈なまでの批判を込めた作品。
これまでも世の中のあり方に対してのメッセージを込めた作品を作ってはいたものの
これほどまでに、圧倒的に表現したものはなかった。
青春をグリーンデイで過ごした誰もが、彼らのメッセージにショックを受けた。
あの、グリーンデイが世界を歌っている。
俺達は、そういう時期に来ている。
明るく、バカ騒ぎしながら、社会への不満をのたまうだけの子供ではいられない。
世界が間違っているのならば、それを変えられるのは我々だ。
ダークなイメージが漂い、作風も変化したアルバムでありながら
新たな層はもちろん、これまでのファンが一人残らず支持した背景には
「一緒に大人になってきた」という事実ではないだろうか。
彼ら自身の殻を破るという意味でも非常に素晴らしかった出来だった上に
世界を動かしたという歴史的な意義を持った超名盤。
|
|
その1へ |
|
|